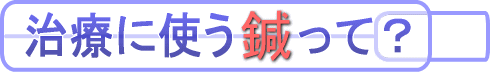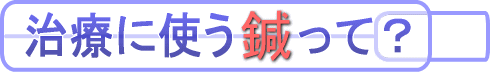|
鍼が刺さるのに痛くない理由
はり治療に、抵抗感がある方のほとんどは、注射や、画鋲などの針が刺さった時のことを思い浮かべてしまうのでしょう。指先にちょっと刺さっただけで、痛くて不快なのに、あんな長い針を刺したら…、なんて想像しただけでぞっとするでしょう。
一般的な注射針は、薬などの液体を体内に注入する目的上、管状になっています。先端はナイフのように鋭く(下図)、皮膚面を切るようにして体に刺し込むので、痛みを感じます。(昔よりはずいぶん改良され、あまり痛くないように工夫されてはいます)
鍼治療用の「はり」は、先が縫針のようになっていて(図)、縫針よりもずっと細く、皮膚に滑り込むよう刺さっていくので、刺激が少なく痛みを感じにくいのです。
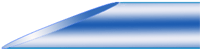
|
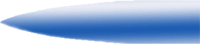
|
| 注射針の先端 |
鍼の先端 |
その上、鍼を刺す時に、「鍼管(しんかん)」と呼ばれる、筒状の器具(写真3)を使うことで、更に、刺す時の痛みを抑えられます。鍼管は、鍼よりやや短いので、鍼先が皮膚に接した状態で、「鍼柄(しんぺい)」(図1))が、少し余ります(下図)。この鍼柄を、指先で軽く叩けば、鍼先が、瞬く間に体に刺さります。これは「管鍼法(かんしんほう)」と呼ばれる方法で、いつ刺されたのか、気付かないぐらいです。当院は、主にこの方法を採用しています。
他に、鍼管を使わない「撚鍼法(ねんしんほう」などの方法もあります。これは、鍼体(しんたい)を持って、そのまま一瞬にして、刺入する方法で、これも痛くありませんが、多少コツがいります。そこで、日本で、誰でも簡単に、鍼が刺せるように、「管鍼法(かんしんほう)」が考えだされたそうです。
どのくらい深く刺さるのか?
治療時には、患者さん自身、ベットに寝てしまうので、なかなか直接針が刺さっている状態を見ることはないでしょう。
鍼の長さには様々なものがあり、よく使われるのは5cm前後の鍼です。当院で、主に使用している鍼も、約4cmです。
“長い”と感じるかと思いますが、鍼の長さと、実際刺さす深さは違います。1mm程度に浅く刺すこともあります。刺し方も、皮膚に対し、垂直、斜め、水平と様々です(下図)。
ツボは全身にあり、症状によって、いくつかのツボを選び、それぞれ刺す方向や、深さを決めます。もちろん、解剖学的な知識に基づいて治療するので、危険なまで深く刺すことはありませんし、どの場所を刺してはならないかは把握しています。
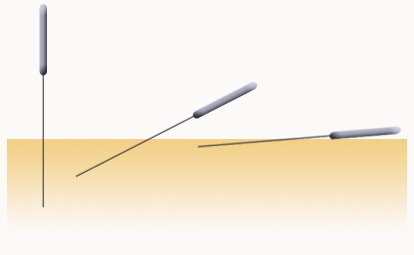 |
| 左から、直刺、斜刺、水平刺 |
鍼の種類
紹介したのは、“鍼治療”に使用する、一般的な鍼です。その他にも、皮内鍼、円皮鍼、梅花鍼、小児鍼など様々な種類があり、必要に応じて使用します。
使用法も、皮膚表面に貼り付けておく、こする、たたく等様々です。、鍼治療とは刺す方法だけをいうわけではないのです。
| 皮内鍼 |
皮膚の直下に、浅く刺したまま1週間程度貼り付けておく、5mm程度の小さな鍼。絆創膏で留めてあるので、それを剥がせば簡単に外せます。 |
| 円皮鍼 |
皮内鍼と同じく、貼り付けたままにしておく鍼。絆創膏の中央に、小さな画鋲のような形をした鍼がついている。 |
| 梅花鍼 |
柄の部分がしなる小型の金槌(かなづち)のような形をした鍼。その槌の部分に梅の花の様に鍼が配置してある。皮膚の上を、軽くたたきながら刺激するために使用する。 |
| 小児鍼 |
主に、赤ちゃんや小さな子供の治療のための刺さない鍼。皮膚をこすったり、さすったりして刺激をするために使用する。棒状だったり、バチの形や、刀のような形のものなどいくつか種類がある。 |
|