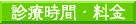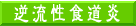| スポーツ障害のタイプ |
スポーツ障害には「急性の外傷」と「慢性の障害」があります。
|
外傷(捻挫、肉離れ、脱臼、骨折など)は、比較的若い人によくみられます。疲労骨折や組織の変性などの慢性のケガは、子どもから大人までだれにでも起こり、特に、成長期の子どもに、使い過ぎによる障害が多くみられます。
|
障害は、スポーツのやり過ぎや、体の特定部分の使い過ぎによって起きるもので、別名「使い過ぎ症候群」とも呼んでいます。
|
| 治療とトレーニング |
痛みなどの障害が起こった時は、放置せず、受診してきちんと治療を受けることが大切です。ただ、全身を安静にする必要はなく、むしろ、ケガの治療中も、痛まずにできる運動を行っておくほうが、治療後、運動を再開する時に、スムーズに復帰できます。
肩のケガであれば、ジョギングをする、膝の障害の場合は、上半身の筋力トレーニングをするなど、ケガをした部位に響かない運動を続けるようにするとよいでしょう。
|
| ケガなど急性外傷の R I C E 処置 |
RICE(ライス)の処置は外傷(打撲や捻挫、骨折など)の直後から行われる重要な治療法です。
Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)のことです。
|
| Rest(安静) |
痛みや腫れを軽減させる目的で行われます。三角巾や包帯などで患部を安静にさせます。
骨折や靭帯損傷がある場合はギプス固定を行います。
|
| Ice(冷却) |
局所を冷却することにより、組織の血管は収縮し腫れや炎症反応が抑制されます。又、冷却により痛みを認知する神経線維の伝導速度が遅延し、筋肉の異常な緊張や発痛物質の発生が抑制されます。
冷却温度を10℃前後(季節によっては温度を変更します)に設定し、感覚がなくなる程度に冷却します。自宅では氷パックを用いて1日に2〜3回、受傷後3日間行います。
|
| Compression(圧迫) |
内出血や腫脹(はれ)を抑える目的で行われ、処置としては弾力包帯などで圧迫します。
|
| Elevation(挙上) |
腫脹を抑える目的で行われ、処置として患部を心臓より高く挙上し静脈還流を促します。
|
|
ケガによる腫れは、内出血、組織液の滲出などの炎症反応です。これらを早期に、最小限に、抑えることが治療のポイントであり、ケガの予後を大きく左右します。放置すると、周辺の筋肉や関節まで蔓延し、スポーツ活動の復帰にも大幅に影響します。
打撲、捻挫、肉離れなど、スポーツ傷害には、鍼治療や筋膜療法などを行うことで、回復も早くなります。
|
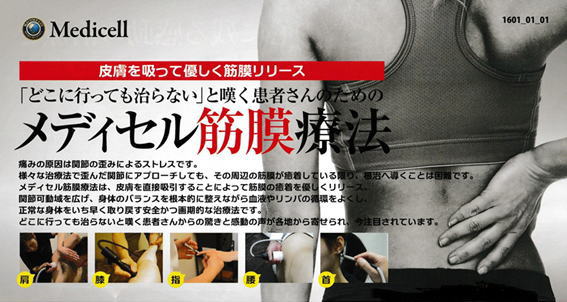 |