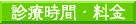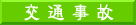|
|
 |
生後2〜3カ月から1歳半くらいの幼児によくみられる原因不明のもので、空腹やおむつの濡れ、寒さ、発熱など特定の原因のある場合は含まれません。一定の睡眠リズムを作るための成長過程の一面と考えられていますが、病気のときもあるため注意が必要です。
|
 |
生後8カ月頃から2〜3歳までにみられる神経の異常興奮で、小児の自律神経の失調と考えられます。自我の成長過程で、欲求が満たされず、ストレスからイライラして大声を上げたり、物を投げたりします。一般に言葉がはなせるようになると、自然に消失します。
|
 |
3〜6歳の小児に多く、眠りについてからしばらく後、突然飛び起パニック状態になり、長くても10分程でまた眠ってしまいます。日中の精神的興奮や緊張がきっかけで起き、深い眠りについている間に悪夢をみて、半覚醒(脳は寝ていて身体が目覚めている)状態になっているため、完全に目覚めさせるのは困難で、朝になっても覚えていません。
生まれつきの、睡眠と覚醒の調節機能の不調が原因と考えられますが、一般に、成長するに従って自然に治ります。
|
 |
消化器系疾患参照
|
 |
小児の偏食は、主に離乳食から幼児にかけての食生活によって起りますが、親や周囲の食習慣や先入観にも左右されます。激しい偏食は味覚だけで無く臭覚の幅も狭め、栄養の偏りから心身の不調の原因となります。偏食の多い小児はこだわりが強く、性格的な偏りもあると考えられるため、栄養面からの強制的な食事指導は避け、根気よく長期にわたる指導が必要です。
|
 |
原因によって、胃腸など消化器に問題があったり他の病気の影響で起る食欲不振と、ストレスや不安感などの精神的なものがあります。また、生まれつきの体質で小食な場合もあり、原因を特定する事が食欲回復の第一歩でしょう。
|
 |
なかなか寝つけない、夜泣き、夜驚など小児の睡眠障害は脳の睡眠調節機能が未熟なために起ることが多く、一般に、成長と共に自然に治ります。不眠を起こす直接的な原因は、生活習慣の乱れ、精神的興奮やストレスの他、寒さや音、光などの物理的な刺激も考えられます。
|
 |
気管支にアレルギー性の炎症が起きているため、粘膜が敏感で、わずかな刺激で気道が狭くなり呼吸困難の発作を起こします。原因は明らかにされていませんが、生まれつきの体質やダニ、ハウスダスト、天候などの環境要因、精神的ストレスが発作を誘発します。重症の場合、生命に危険の及ぶ場合もありますが、根気よく治療と生活改善を続けることで、大半は軽快、治癒します。
|
 |
アレルギー性湿疹やアトピー性皮膚炎、小児喘息はみなアレルギー性の病気の症状です。アレルギーは、本来は細菌など外から体内に侵入した異物を排除し身体を健康に保つ免疫機構の不調で、特定の異物に過剰反応しでしまい、様々な症状をあらわします。免疫の過剰反応の原因はまだ明らかにされていませんが、アレルギー性湿疹の場合、ダニやハウスダスト、たまごなどの食物、日光などの刺激で皮膚に湿疹やかゆみが起きます。
|
 |
流行性と反復性があります。流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の原因はウイルスで、3〜6歳児の多くみられ、一度かかると再び発症する事はありません。反復性耳下腺炎は何度も耳下腺が腫れて、通常12歳頃になると治りますが、原因は解明されていません。
|
 |
夜尿症は、膀胱容量が小さかったり不眠や精神的ストレスなどいくつかの原因が複雑に絡んでいる場合が多く、遺伝的要素も強いと考えられます。多くは成長と共に軽快しますが、膀胱や腎臓、ホルモンの病気の症状としてみられる場合もあり、子供の心理的、社会的影響を考慮し持続的に治療を受けましょう。
|
 |
特定の身体的な病気ではありませんが、症状の特徴から4つのタイプに分類されます。胃腸虚弱で小食な胃腸タイプ、風邪や中耳炎などにかかりやすい呼吸器タイプ、疲れやすく顔色の悪い 循環器タイプ、神経質で怒りやすく夜驚などを起こしやすい神経タイプで、いくつかのタイプが重複している場合が多くみらます。根気よく治療を続ける事で、体力がつき心身が安定して症状が軽減します。
|